【Japanese food】Basic Dashi broth【What is Umami?】/だしの種類と基本のだしのとり方
『うま味――第5の味の秘密を解き明かす(Umami: Unlocking the Secrets of the Fifth Taste)』
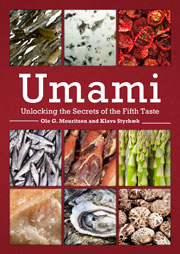
うま味
ウィキペディア(Wikipedia) より
うま味は、主にアミノ酸であるグルタミン酸、アスパラギン酸や、核酸構成物質のヌクレオチドであるイノシン酸、グアニル酸、キサンチル酸など、その他の有機酸であるコハク酸やその塩類などによって生じる味の名前。五基本味の一つ。
うま味物質は、東京帝国大学(現在の東京大学)教授だった池田菊苗によって、1908年にだし昆布の中から発見された。最初に発見されたうま味物質はグルタミン酸である。うま味となるだし昆布や鰹節を使用した出汁は、日本料理の基本となる伝統的調理手順のひとつである。
【名称】
「うま味」の命名は、その成分物質がグルタミン酸であることを発見した池田菊苗による。池田は、それまでに知られていた酸味(さんみ)・甘味(かんみ)・塩味(えんみ)・苦味(にがみ)の四基本味に加わるべき第5の基本味としてこれを「うま味(うまみ)」と名付けた。なお、発表当時からこの表記である。
日本国外、特にその存在の認知が遅れた欧米諸国の言語では、従来この「うま味」に相当する表現が存在しなかったため、現在のところ日本語を借用した「umami」を便宜上代用している場合が多い。ただし、英語の「savory」(肉料理の風味がある)や「brothy」(肉の煮汁の風味がある)、中国語の「鮮味」、そしてこれらに相当する各国語の表現を使用する試みも見られている。
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
『人体大全 なぜ生まれ、死ぬその日まで無意識に動き続けられるのか』
ビル・ブライソン/著、桐谷知未/訳 新潮社 2021年発行
第6章 あなたの「入り口」は大忙し より
味覚受容体は口内以外にも存在する
ヒトは約1万個の味覚受容体を持っているが、実は口の中には痛覚その他の体性感覚の受容体がさらに数多くある。そういう受容体が舌の上に並んで存在するので、わたしたちはたまに取り違える。トウガラシを”ホット”と表現すると、意外にも正確な事実を語っていることになる。脳は実際に、それを火傷と解釈しているからだ。コロラド大学のジョシュア・テュークスペリーはこう述べた。
「トウガラシは、335度のバーナーに触れたときに活性化するのと同じニューロンを刺激する。つまり脳は、舌がコンロで焼かれていると警告しているのだ」。同様に、メント―ルは煙草の熱い煙に混じっていても冷たいと感知される。
あらゆるトウガラシの活性成分は、カプサイシンと呼ばれる化学物質だ。カプサイシンを摂取すると体がエンドルフィンを放出し――なぜなのかはさっぱりわからないが――じんわりと熱い喜びを覚える。しかしあらゆる熱さと同様、それは急速に不快になり、次に耐えがたいほどになる。
・
カプサイシンは血圧を下げ、炎症を抑え、がんにかかりにくくし、ほかにもさまざまな面でたいていの人の健康に役立つと報告されてきた。《ブリティッシュ・メディカル・ジャーナル》誌で報告されたある研究では、カプサイシンをたくさん摂取した中国の成人は、あまり食で冒険しない人に比べて、死因を問わず、死亡する確率が14パーセント低かった。しかし、こういう”発見”によくあるとおり、辛い食べ物をたくさん食べた被験者の生存率が14パーセント高かったのは、単なる偶然かもしれない。
ちなみに、痛覚受容体は口の中だけでなく、目や肛門や膣にもある。だから辛い食べ物は、ときどきそういう部分にも不快感を引き起こす。
「うま味」の発見
味覚について言えば、わたしたちの舌が識別できるのは、おなじみの甘味(かんみ)、塩味(えんみ)、酸味、苦み、うま味(umami 風味のよさを意味する日本語)しかない。一部の専門家は、金属、水、脂肪、そしてこく味という”芳醇さ”あるいは”濃厚さ”を意味するもうひとつの日本の概念に割り当てられた特別な味覚受容体もあると考えているが、広く認められているのは5つの基本味の受容体だけだ。
欧米では、うま味という概念はいまだに少し異国的に感じられる。その味は何世紀も前から知られていたものの、実は日本でも比較的新しい用語だ。出汁(だし)と呼ばれる、海藻と乾燥させた魚を煮出した汁から生まれる味で、他の食物に加えるとさらに美味になって、筆舌に尽くしがたいが、とても特徴的な風味が醸し出される。1900年代初め、東京の化学者、池田菊苗は、その風味の源を突き止めて合成してみることにした。1909年、池田は、風味の源がアミノ酸のひとつの化学物質グルタミン酸塩であることを特定したという短い論文を、東京のある学術誌に発表した。そしてその風味を、”おいしさの素”という意味の「うま味」と名づけた。
池田の発見は、日本の外ではほとんど注目を集めなかった。うま味という言葉は、1963年に1編の学術論文に現われるまで、英語ではどこにも記録されていない。知名度の高い出版物に最初に現れたのは、1979年、《ニュー・サイエンティスト》誌でのことだった。うま味の味覚受容体が欧米の研究者たちに確認されたのち、2002年に、池田の論文がようやく英語に翻訳された。しかし日本では、池田は化学者としてよりむしろ、のちに大企業となる味の素の共同創立者として有名になった。取得した特許を利用して、今ではグルタミン酸ナトリウム(MSG)として広く知られているうま味調味料をつくるために創立した会社だ。現在、味の素はグローバル企業に成長し、全世界のMSGの約3分の1を製造している。
MSGは、欧米では1968年以降、散々な目に遭わされてきた。当時《ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシン》誌に、ある医師からの手紙――論文や研究ではなく、単なる手紙――が掲載された。そこには、中華料理店でで食事をするとたまに具合が悪くなることがあり、料理に加えられたMSGが原因ではないかと疑っていると書かれていた。その手紙につけられた見出しは、”中華料理店症候群”で、この小さな始まりから、大勢の人のあいだでMSGは一種の毒だという考えが定着した。しかし実際には、そんなことはない。MSGは、たとえばトマトなど、たくさんの食品の中に自然に存在し、正常な量を摂取した場合に悪影響が現われた例はまったく見つからなかった。オーレ・G・モウリットセンとクラフス・ストルベクの興味深い研究所『うま味――第5の味の秘密を解き明かす(Umami: Unlocking the Secrets of the Fifth Taste)』によると、「MSGは、史上最も徹底的な調査を受けてきた食品添加物」であり、それを糾弾しうるなんらかの根拠を発見した科学者はひとりもいないにもかかわらず、欧米では頭痛や軽度の不調の原因という評判が衰えず、いつまでも消えそうにない。
舌とその味蕾は、基本的な食感と食物の性質を教えてくれるだけだが――柔らかいか、滑らかか、甘いか苦いか、などなど――すべてを完全に味わうには、他の感覚にも頼る必要がある。当然のように誰もがしていることだが、食べ物の味について話すとき、たちていは言葉の使いかたが間違っている。食事のときわたしたちが味わっているのは風味で、味に匂いが加わったものだ。
匂いは、風味全体の少なくとも70パーセントを占めると言われ、もしかすると90パーセントにもなるかもしれない。わたしたちはあまり考えずに、これを直感的に理解している。誰かにヨーグルトの瓶を渡されて、「これはイチゴ味?」ときかれたら、あなたはふつう、口に入れずに匂いを嗅ぐだろう。それは、イチゴ味が実際には口で感知される味ではなく、鼻で感知される匂いだからだ。
食事をするとき、ほとんどの香りは前鼻腔経路と呼ばれる鼻孔からではなく、後鼻腔経路として知られる鼻腔の裏側から届く。味覚の弱点を知る簡単な方法として、目を閉じて鼻をつまみ、ボウルに入れた風味つきのゼリービーンズを手探りで選んで食べてみてほしい。甘さにはすぐに気づくだろうが、ほぼ確実に、風味はわからないだろう。しかし目をあけて鼻孔を広げれば、特定の果物の風味がすぐさまはっきりしてくる。