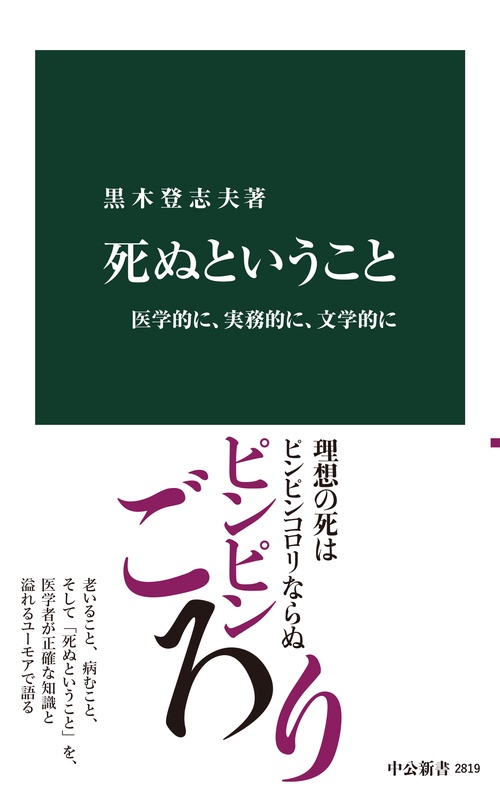
中公新書 死ぬということ――医学的に、実務的に、文学的に
黒木登志夫【著】
【目次】
はじめに
第1章 人はみな、老いて死んでいく
第2章 世界最長寿国、日本
第3章 ピンピンと長生きする
第4章 半数以上の人が罹るがん
第5章 突然死が恐ろしい循環器疾患
第6章 合併症が怖い糖尿病
第7章 受け入れざるを得ない認知症
第8章 老衰死、自然な死
第9章 在宅死、孤独死、安楽死
第10章 最期の日々
第11章 遺された人、残された物
第12章 理想的な死に方
終章 人はなぜ死ぬのか――寿命死と病死
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
『死ぬということ――医学的に、実務的に、文学的に』
黒木登志夫/著 中央公論新社 2024年発行
「死ぬということ」は、いくら考えても分からない。自分がいなくなるということが分からないのだ。生死という大テーマを哲学や宗教の立場から解説した本は多いが、本書は医学者が記した、初めての医学的生死論である。といっても、内容は分かりやすい。事実に基づきつつ、数多くの短歌や映画を紹介しながら、ユーモアを交えてやさしく語る。加えて、介護施設や遺品整理など、実務的な情報も豊富な、必読の書である。
はじめに より
高校生にわからないのは当然として、80歳を過ぎても死の瞬間のことはわからない。いったん死んで帰ってきた人の話はたくさんあるが、できすぎた感じがして信用できない。そもそも、われわれはなぜ死ななければならないのか。「死ぬということ」とはどういうことなのか。ベッドに入ってから考えたとしても、いつの間にか眠ってしまう。漠然とした問いを漫然と考えている限り、いつまでたっても明確な答えには到達しない。
死に関する本はたくさんある。そこに新しく加える以上、何らかの新しい内容でなければ受け入れられないであろう。本書を書く前に、死に関する本をたくさん買い求め、目を通した。わかったのは、意外にも医学の観点から書かれた死の本がほとんどないことであった。私は、これまで、がん、COVID-19など、病気の本を何冊も書いてきた。2007年には、『健康・老化・寿命』という本を出版している。ついにゴールの本を書くときが来た。それは、人並み以上に歳を重ねた自分のための本にもなるはずだ(何しろ、米寿なのだ)。
・
死後の世界を信じる読者には本書は期待はずれであろう。私は死後の世界はないと信じている。死ですべては終わるのだ。しかし、生きた証は、人びとの心の中に残っている。それでよいのだと思う。「死の瞬間」についても一言も書かなかった。再現性のない経験談だけでは、科学的検証の対象にならず、既存の書の受け売りに終わってしまうじからである。私自身、大空を飛んだり、スキーで大斜面を滑降するような気分のよい夢は何回も見ているが、朝にはちゃんと生きていた。「死の瞬間」にも素晴らしい夢を見るかもしれないが、それは誰にも教えずに永遠の秘密にしておこう。
最後にネタバレをしておこう。本書には、少なからず常識に反するふたつの主張がある。
第1は理想の死に方である。国内的常識である「ピンピンコロリ」ではなく「ピンピンごろり」をすすめていることだ。小説でも、オペラでも、交響曲でも、最後は荘厳なフィナーレで終わる。人生という一大事業があっけなく終わったのでは、あまりにも寂しい。最後は、ゆっくりとお世話になった人と語り合い、感謝するだけの時間を残して、人生に別れを告げてほしい。自分が苦しみたくないというだけの理由で、人生の後始末もせず、「コロリ」と死ぬのは身勝手というものである。ただし、十分に年をとり、死んでも不思議ではないと口に出さなくともみんなが思っており、さらに迷惑をかけないように準備のできた人であれば「ピンピンコロリ」は悪くない。介護の世話にならない点でもおすすめである。
第2は、世界の常識へのチャレンジである。老衰死(第8章)を書いているときに、日本は老衰による死亡が増え続け、死因ランキングの第3位であるにもかかわらず、日本以外の国には老衰による死亡が全くないという意外な事実に気がついた。なぜなのか。調べているうちに、WHOは、病気による病死と事故などのよる死亡のみを死亡原因として認めていることがわかった。日本の老衰死は、単に年をとったゆえに死んだのではない。寿命の限界に近づたから死んだのだ。
どこの国でもいつの時代でも、ジャンヌ・カルマン(最も長生きをしたとされているフランス人女性)を除けば(第2章)、人間の寿命は117歳が限界である。老衰は、その意味で「寿命死」と呼ぶべきと考え、終章「人はなぜ死ぬのか」を書いた。私は「寿命死」の考えを世界に広げようと考えている。最後は、自分の死をもってそれを証明するつもりだ。