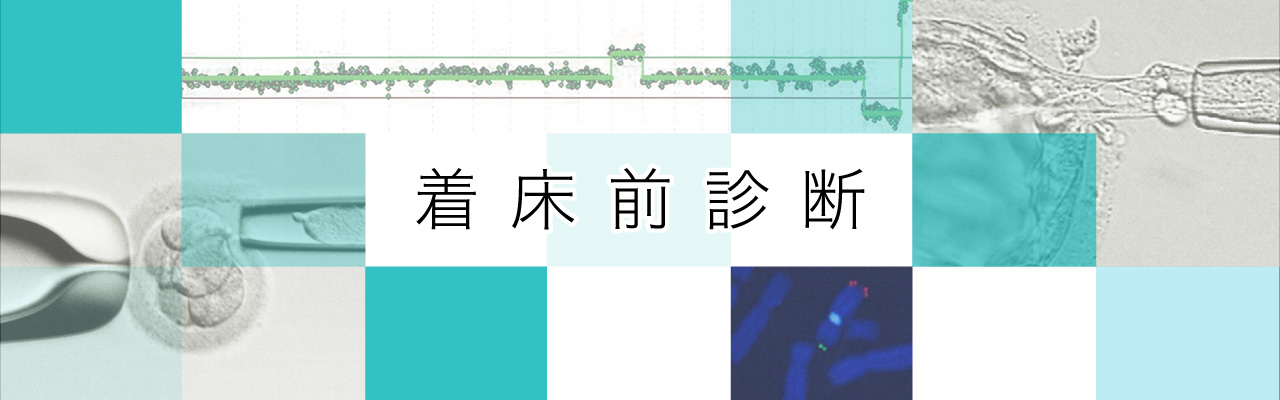着床前診断の検査法
医療法人オーク会
●着床前診断の検査法
着床前診断に用いられる検査は、染色体を調べる検査と遺伝子を調べる検査があります。
https://www.oakclinic-group.com/pgd/kensa.html
死因の人類史
【目次】
序章 シエナの四騎士
第1部 さまざまな死因(死とは何か?;『死亡表に関する自然的および政治的諸観察』 ほか)
第2部 感染症(黒死病;ミルクメイドの手 ほか)
第3部 人は食べたものによって決まる(ヘンゼルとグレーテル;『壊血病に関する一考察』 ほか)
『死因の人類史』
アンドリュー・ドイグ/著、秋山勝/訳 草思社 2024年発行
疫病、飢餓、暴力、そして心臓、脳血管、癌…人はどのように死んできたのか?
有史以来のさまざまな死因とその変化の実相を、科学的・歴史的・社会的視点から検証した初の試み、壮大な“死”の人類史。
第4部 死にいたる遺伝 第16章 アウグステ・Dの脳 より
アルツハイマー病の早発型と晩期発症型
1901年11月25日、ドイツのフランクフルトにある市立精神科病院に51歳緒女性が入院し、上級医アロイス・アルツハイマーの診察を受けることになった。女性の名前はアウグステ・Dと記録された。1903年、アルツハイマーはミュンヘンの王立精神医学診療所に移ったが、1906年にアウグステ・Dが亡くなるまで、彼女のその後の病状について観察を続けた。アウグステ・Dは夫に対する執拗な嫉妬妄想に続いて、記憶力や理解力の低下や言語障害、不規則な行動、幻覚、妄想などの症状を示すようになり、最初の症状が現れてから5年とたたないうちに死亡した。
死後解剖が行われ、アウグステ・Dの脳に関する詳細な剖検(ぼうけん)も実施されたが、アルツハイマーはそれまで見たことがないようなものを目にしていた。まず、不自然な脳が委縮し、明らかに組織が失われていた。脳内の大半の神経細胞の中心部にもつれた凝集体があり、その異常な厚みと「特有のこわばったもつれ」が際立ち、また細胞の外側、大防皮質には大きな沈着物(プラーク)が見られた。アルツハイマー自身、もつれと沈着物がこの病気の特徴だと述べており、2つの特徴はいまでも剖検でアルツハイマー病と診断される際に用いられている。現在では広範に見られる病気だは、驚くことにアルツハイマー自身がこの症状を持つと報告した患者は1人しかおらず、当時(1910年)はまったく新しい病気だと信じられていた。
遺伝子改変の倫理上の問題
DNAを正確な位置に適切な方法で改変する技術は、現在もっとも注目されている研究分野だ。いちばん広く採用されているのは<クリスパー・キャスナイン>(CRISPR/Cas9)という手法だが、その改良型や代替方法がいまも数多く開発されている最中だ。
この種の実験はヒトのDNAを変えることで、人間を「改良」「強化」しようとする世界への扉を開いていく。これまで遺伝子学者は病気を起こす突然変異をずっと探してきたが、<A673T>のように病気を予防する変異も少ない可能性もある。実際、<A673T>に続いて、認知症を予防して寿命を延ばすとされる第2の変異が発見されている。もっとも、APP(アミロイド前駆体タンパク質)の塩基配列が正常だった場合、<A673T>のSNP(個人間の遺伝情報のわずかな違いのこと)を挿入してもアルツハイマー病が治るわけではない。その意味で、ハンチントン病(筋肉のひきつりやけいれんを起こす病)を引き起こすことが確実視されているハンチンチン遺伝子の<CAG>リピートを取り出すこととは根本的に異なる。
・
このような方法でDNAの改変を始めるには、それに先立って、数多くの現実的な問題と倫理上に問題に向き合わなくてはならない。第1に、遺伝子改変を目的とする技術はまだ十分信頼できるものではないという現実だ。潜在的な問題はいくつかあるが、なかでも必要な変異とともに、欠点をともなう変異wp挿入したり、細胞の一部にしか影響を与えず、ガンを引き起こしたりする可能性が否定できないことだ。また、対外受精が必要になる場合も考えられるが、対外受精は高い失敗率をともなう。
たとえ、DNAを考えたとおりに完璧に変化させられたにせよ、その変化がどのようなものになるのかは正確に予想できない。毎回ハンチントン病を引き起こす<CAG>リピートのような明確なケースのほうこそまれなのだ。同様に、血圧に関係すると思われる何百もの遺伝子も、血圧以外の無数の生物学プロセスに影響を与えるだろう。ほかの現象に何も影響を与えないまま、高血圧になりやすい体質だけを変えるのは不可能なのだ。遺伝子はたがいに途方もなく複雑に作用しあっており、年齢や環境、体内の部位によっても変化してしまう。
中年期に心臓発作を起こす確率を変えてしまえば、ほかの年代や体の部位に予期しないさまざまな結果が現れるかもしれない。さらに言うなら、やがて新しい精子や卵子に成長する胚の細胞に手を加えているのだから、その誤算は増幅されながら未来の世代に受け継がれていくことになる。
かりにこの技術が最終的に信頼できるものになれば(原稿執筆時点では、向こう見ずな一部の科学者がそれを推し進めているが、まだ実現はしていない)、遺伝性疾患の治療が進められるかもしれない。その場合、ひとつの遺伝子に変異があることと、その病気が発症することとのあいだに、単純かつ直接的な関係がある疾患の治療にばるだろう。たとえば、ビクトリア女王が持っていた第Ⅸ因子に起きた変異で発症する血友病をはじめ、鎌状赤血球症、嚢胞性線維症(消化管や気道の分泌液異常)、フマラーゼ欠損症、ハンチントン病などの遺伝性疾患などだ。アルツハイマー病については、早発型の原因とされるプレセニリン1、プレセニリン2、APPに起こる優生突然変異を修正することもできるだろう。こうした変異にはなんの恩恵もうかがえず、明らかに大きな害だけをもたらしている。ひとつの遺伝子の異常で引き起こされるいわゆる「単一遺伝子疾患」には、全部で3000近くの疾患があることがわかっている。これらは、遺伝性疾患をなくそうというDNA編集の最初の候補となる疾患だ。
こうした考えをさらに推し進め、単一遺伝子疾患を安全に修復できるなら、それを行わないのはむしろ倫理にもとると説く人もいるだろう。たとえば、二分脊椎症(胎児期の脊髄や脊椎の異常)を予防するため、妊娠中、妊婦は葉酸を摂取して、胎児をケアすることが道徳的な義務とされる。それなら、恐ろしい遺伝的障害を抱えながら、短くて悲惨な人生を送らないために胚のDNAを編集することも道徳的な義務のはずだ。筋ジストロフィー(筋肉が徐々に弱っていく病気)に苦しむ自分の子供に、生まれる前にDNAを編集すれば病気を未然に防げたのに、それをしなかった理由を説明できるだろうか? とはいえ、胚のSNPをスクリーニングして移植する胚が選択できるようになれば、DNAを編集する必要はほとんどなくなる。
一方、遅発型のアルツハイマー病を発症する可能性には、何十もの遺伝子変異の影響がかかわっている。それらの変異はまだ十分に解明されていない複数の影響を与えているだけではなく、その多くは人体の役に立っていることも考えられる。何が起きているのか、その理解がさらに深まるまで、これらの変異には手を出すべきではないだろう。健康状態とはもっぱらこのような仕組みで作用しており、数百とは言わないまでも、数十もの遺伝子の棒ダな数のSNPのすべてが小さな影響を人体に与えている。疾患だけではなく、その点では身長や知能といった形質も例外ではない。
また、生活習慣が確実に変化している以上、生活習慣病のためにDNAを変化させてもあまり意味はないだろう。魅力的だが糖分の多い食べ物の影響に対処するため、50年後も苦労しているかどうかなど誰にもわからない。DNA編集とはごくかぎられた疾患への対処法であり、それ以外のあらゆる疾患に用いるのは誤っており、とくに解決策がすでにある病気の場合はなおさらなのだ。