【科学の名著】生命とは何か|シュレディンガー ~新しい視点で生命について考えてみよう~
動画 YouTube
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=-5oUst5h8yM
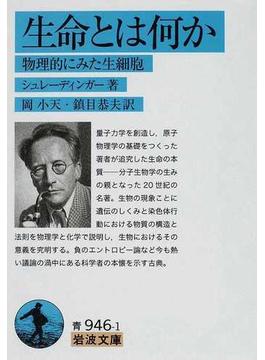
生命とは何か 物理的にみた生細胞 (岩波文庫)
著者 シュレーディンガー (著),岡 小天 (訳),鎮目 恭夫 (訳)
https://honto.jp/netstore/pd-book_03005473.html
『生命と非生命のあいだ』
小林憲正/著 ブルーバックス 2024年発行
第1章 生命はどこから来たのか 生命は何者か より
シュレーディンガーの生命観
オーストリアの物理学者エルヴィン・シュレーディンガー(1887~1961)は、量子力学の創始者の1人として有名で、1933年にはノーベル物理学賞を受賞しました。しかしその後、生命に興味を持ち、1944年に『生命とは何か』という本を著したこともよく知られています。
彼が生命に興味を持ったきっかけとしては、20世紀前半に、「遺伝」のしくみが徐々に解き明かされてきたことがあります。19世紀に、細胞の中に「染色体」とよばれる棒状の構造体が見つかりました。20世紀に入り、トーマス・ハント・モーガン(1866~1945)らにより、染色体に遺伝をつかさどる物質が含まれていることがわかりました。「遺伝子」よよばれるようになったこの物質を、シュレーディンガーは、大きなタンパク質だろうと考えていました。遺伝というまさに生命と非生命を分かつ重要なものが、物理・化学で解明できる期待が高まっていました。なお、遺伝子の本体がタンパク質でなく、核酸という別の高分子であることがわかったのは、『生命とは何か』出版と同じ1944年、米国の細菌学者オズワルド・エーブリー(1877~1955)によってでした。
シュレーディンガーは『生命とは何か』の中で、物理学者による新たな生命観を提示しました。熱力学の第二法則から、孤立した系において、「乱雑の度合い」をあらわす「エントロピー」が増大していきます。たとえば、ビーカーに入った水に色のついた液体をたらすと、色のついた部分は徐々に広がり、最終的には溶液全体に均一に広がりますが、それがもとに戻ることはありません。しかし、生物の中では生体分子や組織や器官がつくりだされていく、つまりエントロピー(乱雑さ)が減少していくように見えるのです。このことをシュレーディンガーは比喩的に「生命とは負のエントロピーを食べているもの」と言いました。
その後、1953年に、ロザリンド・フランクリン(1920~1958)、ジェームズ・ワトソン(1928~)、フランシス・クリック(1916~2004)らの働きによって、DNAの構造が解明され、核酸(DNA)が遺伝をつかさどる物質であることがわかりました。これをきっかけに、「分子生物学」という、シュレーディンガーが期待したような物理学的手法を用いた生物学が誕生したのです。
・
シュレーディンガーは著書のなかで生命の起源について直接的には言及していませんが、最後に生命のことを「量子力学の神の手になる最も精巧な芸術作品」と表現して結んでいます。生化学者であるオパーリンは後年の著作『生命ーその本質、起源、発展』(1960)のなかで、シュレーディンガーの言葉は神による生命の起源を認めている、と批判しています。
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
じじぃの日記。
小林憲正著『生命と非生命のあいだ』という本に「シュレーディンガーの生命観」があった。
生命とはなにか
ネットで「生命とはなにか」をキーにして検索してみた。
「遺伝」と「進化」、そして自己複製
「生理学的」あるいは「代謝的」定義は、近代科学が発展する以前の大昔から、生命の定義としてポピュラーなものであった。
一方で、次の「遺伝的」定義は、ダーウィンによる進化論の登場や、遺伝のメカニズムの解明、DNAなどの分子生物学の発展を経て、生命の定義の中でも中心的な観点になってきた。遺伝や進化の前提としてはまず、生命は自らを精密に複製するということがある。この自己複製こそ、生命の最も生命らしい活動といえるだろう。
(https://gendai.media/articles/-/113625?page=3)