「直腸がんのda Vinci手術」解説【倉敷中央病院】外科
動画 YouTube
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=CK0Rm1e4hWg
直腸がんの手術
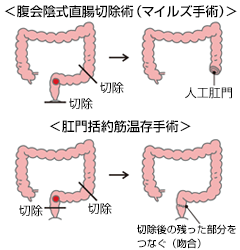
大腸がん(直腸がん・結腸がん)の治療と予防
おなかの健康ドットコム
<直腸がん>
肛門近くの直腸にできた早期がんは、開腹せずに肛門のほうから切除する「局所切除術」を行います。肛門括約筋(かつやくきん)(肛門を開閉する筋肉)を切らない方法と切る方法があります。
肛門側から取れないがんは開腹手術になります。直腸がんの手術には大きく分けて2つあります。ひとつはがんのある直腸と共に肛門も切り取ってしまい、結腸に人工肛門を作る方法です(直腸切断術)。もうひとつは肛門括約筋を残して結腸と肛門管、あるいは残った直腸をつなぐ肛門括約筋温存切除術です。
現在は患者さんのQOL(生活の質)を考慮して、ほとんどが肛門括約筋温存切除術を行うようになりました。
https://www.onaka-kenko.com/various-illnesses/large-intestine/large-intestine-cancer/03.html
すばらしい医学―あなたの体の謎に迫る知的冒険
【目次】
はじめに
第1章 あなたの体のひみつ
第2章 画期的な薬、精巧な人体
第3章 驚くべき外科医たち
第4章 すごい手術
第5章 人体を脅かすもの
おわりに
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
『すばらしい医学―あなたの体の謎に迫る知的冒険』
山本健人/著 ダイヤモンド社 2023年発行
第4章 すごい手術
器械で腸を切って縫う より
「縫う」と「切る」を同時に行う
私は手術前にいつも、「腸を縫うとき、昔は外科医が糸と針で縫っていましたが、今は器械が縫います」
と説明する。すると、ほとんどの人は非常に驚き、そんな便利な器械があるのかと感心する。外科医といえば、針と糸で縫うイメージがあるからかもしれない。
だが、考えてもみてほしい。医療の世界に限らず、世の中の多くの手作業は、技術の進歩によって器械に任せられるようになってきた。
身の回りを見てみると、そのことがよくわかるだろう。
洗濯機、食洗機、掃除機――。家庭には便利な器械がたくさんあるはずだ。「縫う」という作業を考えても、針と糸を使った裁縫は、多くがミシンのような器械に任せられるようになっている。
腸を縫う器械を、一般に自動縫合器という。自動縫合器を使うと、「縫う」と「切る」を同時に行うことができる。まさに、布の端をカットしながらかがり縫いができるロックマシンと同じしくみである(私はよくこう説明するが、裁縫の経験のある少数の人にしか理解してもらえない)。
例えば大腸がんの手術を行う際は、がんの上流と下流で大腸を切除する。このとき、下準備なしに大腸を切ってしまうと、中の便が漏れ出してしまう。一方、自動縫合器を使えあ、切ったラインの両側が自動的に縫い閉じられる。つまり、がんの上流と下流の切りたいラインで自動縫合器を作動させれば、腸に「封をした状態」で摘出できるのだ。
なお、自動縫合器は、ミシンのように糸で縫ってくれるのではない。無数のホチキスの針のような金属で、腸の壁を縫い閉じてくれるしくみだ。自動縫合器のことを「ステープラー」ともいうが、それはまさに、ホチキス紙を綴じるのと同じしくみだからである。
ホチキスと違うのは、自動縫合器の針がホチキスの針よりはるかに小さいこと、そして、ホチキスを数百回打ち込むがごとく、無数の針で細かく縫い閉じ込めことだ。もちろん、この無数の針は一障害、体内に残しておくことができる。かつて手術を受け、腸の縫合がなされた人の体を再度手術する機会はよくあるが、自動縫合器の針の上を「肉が盛る」ように組織が覆い、人体と同化している姿を目の当たりにできる。
縫合不全という合併症
誤って包丁で切った指の傷を数針縫ったとしても、1週間ほどすれば抜糸できる、つまり、最初は糸がなければ傷口は閉じた状態を維持できないが、時間が経つと「糸がなくても傷は閉じたままになる」ということだ。
誰もが当たり前のようにこの事実を受け入れているが、これは、とてつもない人体の機能である。たとえば、木材どうしをねじで留めるとか、紙をホチキスで留めるといった作業をしたとして、「1週間経てばネジやホチキスの針を取っても接着したままになる」などということはありえない。傷の縁を寄せておくだけで自然に組織が再生し、元通りに戻ってしまうというのは、「ふつうのこと」ではないのだ。
実際、糖尿病やステロイド性剤の使用など、何らかの持病で傷の治癒力が落ちている人は少なからずいる。その場合、健康な人なら数日で治る傷が、数週間経ってもなかなか治らないという問題が起こりうる。
傷を縫って1、2週間後に糸を外すと、再びパックリ傷が開く――。その瞬間に私たちは、「傷を治すのは医師ではなく、人体なのだ」という事実を改めて痛感するのだ。
結局のところ、外科医にできるのは「傷を寄せておくこと」だけである。確かに傷を高い精度で「寄せておくこと」は大切だが、実際に傷が治るのは患者自身の力によるものだ。
腸を縫い合わせた場合も、事情は同じである。腸をどれだけ細かく縫合しても、そのわずかな隙間は、人体が自力で組織を再生させることでしか埋められない。治癒力が落ちた人の場合、縫い目にほころびが生じ、数日後に「隙間漏れ」を起してしまうことがある。この現象を医学用語で「縫合不全」という。
手術の際には一寸の隙間もなく縫い合わせにもかかわらず、1週間後に縫合不全を起こし、縫い目がパックリ開いた姿を目の当たりにすることもあるのだ。
縫合不全の発生リスクは、患者自身の治癒力だけでなく、縫い目の部分の腸の丈夫さ、血流の豊富さなどにも関連する。ひとたび縫合不全を起こすと、腸の内容物がお腹に広がり、重篤な腹膜炎を起こす。縫合不全は、命に関わることもある代表的な合併症の1つだ。
ビルロードが世界で初めて胃がんの手術を成功させたのは1880年代だが、1894年時点での胃切除手術後の死亡率は54パーセントと非常に高く、主な死因は縫合不全であった。この割合は、縫合器を含め技術の進歩によってゆるやかに改善してきた。2000年代後半のデータでは、胃の切除後の縫合不全率は0~5パーセントまで低下している。
消化管の手術の中では、骨盤内の奥深くで腸をつなぎ合わせる直腸がんの手術で縫合不全の割合が比較的高く、技術が進歩した近年においても10パーセント前後である。
どれだけ器械が進歩し、外科医が腕を磨こうとも、これをゼロにすることは難しいのだ。