Social interactions and the brain - Science Nation
How Did Our “Social Brain” Evolve?

The social brain hypothesis: the size of the social group is determined by the size of the neocortex
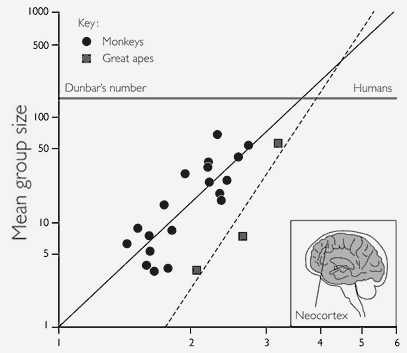
Thinking Big (Featured Book)
Hardcover edition 2014 The Human Journey
Today we all exemplify, and our contemporary culture continues to be driven by, the same social brain - including the community sizes and levels of intentionality - that appeared with the earliest members of our species some 300,000 years ago.
https://humanjourney.us/intercultural-understanding-and-empathy/thinking-big-how-the-evolution-of-social-life-shaped-the-human-mind/
第4章 脳とソーシャル・メディア より
――神経学的要因
ソーシャル・メディアは人間の脳に合うように作られている。どこかに帰属しているという感覚、そして人から認められているという感覚に関わる脳内部位にはたらきかける。報酬系ホルモンであるドーパミンが分泌されるため、私たちはさらに報酬を求めるようになる。さらに人とつながり、関わり、情報を共有したいと思うようになるのだ。私は神経科学者ではないが、私たちの脳がソーシャル・メディア向けに作られている(正確には、ソーシャル・メディアが私たちの脳に合わせて作られていると負うべきだろう)ことを示す証拠がすでに得られているのは知っている。それは驚くべき証拠だ。その証拠の発見につながったのは意外な問いだった。
1980年代のはじめ、ある進化人類学者、認知神経科学者たちのグループが1つの問いを立てた。「人間の脳はなぜこれほど大きいのか」という問いだ。
――社会脳仮説
1980年代から90年代はじめにかけて、オックスフォード大学の文化人類学者、ロビン・ダンバーらのチームは、霊長類の知能に関してある規則性を発見し、それについて詳しく研究しはじめた。
ダンバーらは、1966年に『サイエンス』誌に掲載されたある論文を読んだ。その論文のなかで霊長類学者アリソン・ジョリーは「霊長類の知能の高さは、主に社会的関係の複雑さによって変化する」という主張をしていた。社会関係についての推論は、物体認識(物体を識別し、それについて推論すること)や、物体の操作、食物の収集などに比べてはるかに複雑で難しいのではないかとジョリーは推測した。また、それだけ複雑で難しい推論をしていることは、脳の進化に大きく関係しているだろうとも考えた。社会性の高い種と、社会的行動をあまり取らない種とでは、脳の進化に大きな違いが生じるはずだということだ。
ジョリーは何ヵ月も費やし、マダガスカルのマンドラール川のほとりでキツネザルを観察した。それでわかったのは、キツネザルが非常に複雑な社会秩序を作りあげていることだった。しかも、霊長類の知能の最大の特徴と言う人さえいる物体の認知、操作に関する能力などがさほど高くないにもかかわらず、それを成し遂げていたのである。これは、少なくともキツネザルの場合は、物体の認識や操作のための知能よりも、社会的活動のための知能が重要だったということを示唆する強力な証拠である。
ジョリーは「霊長類は、サルの特徴と考えられていた優れた物体の認知、操作の能力がなくても社会を築くことができる。ただし、霊長類の物体の認知、操作の能力は、霊長類の社会生活のなかでもに進化し得るものである。したがって、社会生活は、霊長類の特徴的な知能に先立つものであり、また霊長類の知能の性質を決定づけたとも言える」と結論づけた。
物体の認知、操作の能力を持っていたから霊長類は賢くなり、社会性を高めたというわけではなかったというのだ。はじめに社会性を高めようとする傾向ふがあり、それが霊長類の持つ知能の性質を決め、物体の認知、操作の能力の獲得につながったというのがジョリーの主張だった。
この大胆な主張を知ったダンバーたちは考えた。社会性が知能の性質に影響を与えるのなら、それは間違いなく脳の発達にも影響を与えるだろうと。まずは、社会の複雑さと脳の発達度合いのあいだに何か進化的なつながりはないか調べはじめた、そのさい、「社会性が高い種ほど、脳は大きくなる」という仮説を立てた。
脳の大きさは簡単に知ることができる。容積と重さを量ればいい。必要なのは、脳の大きさに関連する社会の複雑さを評価する指標である。ダンバーらは、類人猿によく使われる信頼できるであろう指標が1つあるのを知っていた。それは「社会集団の大きさ」である。社会集団が大きくなればなるほど、そのなかに生じる関係は複雑になる。誰と誰が血縁関係であるとか、誰と誰が仲が良い(悪い)とか、誰と誰がどういうことをした、といったことを数多く記録し、考慮しなくてはいけなくなるからだ。つまり、その種の社会集団の平均規模が大きければ、その分だけ、社会は複雑であろうと推測できるということだ。
もし、脳の大きさと社会集団の大きさに相関関係があれば、社会生活のための脳の活動――集団の他の構成員について推論する。他の構成員とうまく関わり、良好な関係を維持するなどの複雑怪奇とも言える活動――が、脳を大きくすることにかなり貢献していると見てよいことになる。
ダンバーらは、人間を含む様々な種の霊長類について、社会集団の大きさの平均値と、脳の大きさの平均値のあいだの関係を調べ、集まったデータをグラフにまとめた。すると、社会集団の大きさと、「通常使い得るあらゆる種類の指標で評価した脳の大きさ」とのあいだには、驚くほど強い相関関係が見られたのだ。
しかし、脳の大きさは、それだけでは、脳の複雑さのとても正確で意味のある指標とは言えない。現在の神経科学者たちは、それよりもはるかに高度な指標で脳の複雑さ表す。そして、脳の複雑さ、知力の指標が高度なものになるほど、社会性の高さとの関係がより強くなることもわかっている。
人間をはじめとする霊長類の脳は、大きく3つの部分に分けることができる。1つは大脳新皮質だ。これは、論理的、抽象的な思考など高次の処理をする部分である。2つ目は辺縁系だ。これは、感情を司る。3つ目はいわゆる「爬虫類脳」だ。これは、生命維持や生殖に関わる部分である。
つまり、ダンバーらの仮説の真の正しさを検証するには、単純に社会集団の大きさと脳の大きさの関係を見るだけではなく、社会集団の大きさと、脳の高次の思考に関わる部分の大きさとの関係を見る必要があるということだ。たとえば、言語や認知などの高次の機能に関わる大脳新皮質とその他の部分の大きさの比である「新皮質比」は良い指標になるだろう。実際、さらに詳しく調査を進めたところ、この新皮質比と、社会集団の大きさなど、社会の複雑さを示す指標のあいだには強い相関関係が認められた(画像参照)。