「彼女は安楽死を選んだ」 NHKペシャル選
動画 dailymotion.com
https://www.dailymotion.com/video/x7us0p7
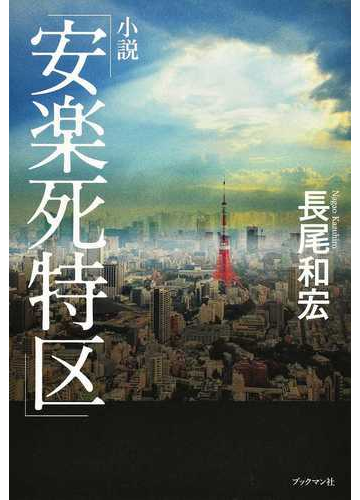
小説「安楽死特区」
長尾和宏 (著)
2024年、「安楽死法案」可決!? 東京オリンピックが終わり、疲弊していく日本で、病を抱え、死を願う男女が、国家の罠に堕ちていく…。医師・長尾和宏の本格医療小説。
【著者紹介】
略歴 〈長尾和宏〉医学博士。医療法人社団裕和会理事長。長尾クリニック院長。関西国際大学客員教授。著書に「「平穏死」10の条件」「糖尿病と膵臓がん」など。
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
小説「安楽死特区」
長尾和宏/著 ブックマン社 2019年発行
女流作家、澤井真子 より
その影響力は平成の終焉とともに終っていたとしても、かつて性愛小説の女神とまでもてはやされた作家の澤井真子が、70歳を目前にしてアルツハイマー型認知症を告白し、それでも書き続けると宣言したというニュースは文芸誌を越えて、テレビや週刊誌にとっても、半日のあいだは世間を賑(にぎ)わすくらいのインパクトはあったようだ。
・
日比谷の高級ブランドショップが並ぶ通りは、何度も訪れている場所であった。しかし、この通り中央の、1階に寿司屋が入っているビルの5階に、認知症外来専門の<ピースフルクリニック>があったことを真子は知らずにいた。
真子はそのクリニックで、「中程度のアルツハイマー型認知症」との診断を受け、その瞬間から「認知症患者」となった。隣で秘書の美和が、一生懸命メモを取っている。桜、猫、電車を逆から言わされるのをテレビで見たことがあったので、真子は必死にその練習をしていったのだが、そうした記憶力の検査はあまり意味がないとされ一昨年で廃止になっていた。スクリーニングとして一般的な知能テストなMMSE検査、甲状腺機能を含む血液検査、そしてCTスキャンやSPECT検査。それらを、国立長寿医療センターが監修したビッグデータにかけて診断がその場で下る。
半日かけてヘトヘトになったが、このままじゃ終われないと、すべてを取材のつもりでしっかり美和にメモを取らせ、ときにはテープレコーダーを回しながら検査を受けた。
その蔦野という名の医師の柔和な顔ならば真子も何度かテレビで見たことがある気がした。高齢の女性が多く来るからであろう。書棚の上にはマリー・ローランサンのシルクスクリーンが立て掛けてある。
「検査の結果、軽度に近い中程度のアルツハイマー型認知症と思われます。脳の血流が少し低下していますね」
わかっていた。そのために今日、ここに来たはずだった。いや、違う。わかっていた悪魔の宣告を、なぜわざわざ聞きに来たのかが、真子はわからなくなっていた。誰の仕業だろう。私はこんな言葉を聞きたくなんてなかった。自分が認知症になったと知ることの意味とはなんだろう。ただ楽に、痛くなく、恥をかくこともなく死にたかっただけなのに。
混乱する真子を宥(なだ)めるように5階の特別診察室からは、日比谷公園の青々とした緑が見えた。その向こうには積乱雲が驚くような速さで動いていて、国会議事堂を包み込もうとしていた。
「アルツハイマー型だと思われる、というのはどういうことでしょうか」
真子は控えめな口調で医師に訊く。心配そうに美和がこちらを見つめている。
「そうに違いないということです。残念ながら、頭のなかをあけて見られるわけではありませんから、検査の結果、そう推測されるということです」
「他の認知症と、どう区別をなさるの?」
「症状からしか区別はできないのです。数年前まではアルツハイマー型の場合は、脳にアミロイドベータというたんぱく質が蓄積することで正常な神経細胞が壊れて脳が委縮すると考えられていました。しかし、それが間違いではないか。原因は他にあるということで、犯人探しの研究が世界各国ではじまっていますが、今のところ真犯人はまだ同定できていません。アルツハイマー型と区別をされている脳血管性認知症、これは、アルツハイマー型についで多く、認知症の約2割を占めると言われています。脳梗塞や脳出血など、脳の血管障害によって起こる認知症です。これは原因がはっきりしています。徐々に脳の機能が低下することで認知症や運動障害が引き起こされます。そして今、急激に増えているのがレビー小体型認知症です」
「ああ、幻視とか幻聴があるっていうあれね。最初は虫が見えるのでしょう?」
・
昔どこかで聞いたことのあるリズムと音階で、一音一音切りながら月刊誌副編集長の高城はその5文字を吐いた。
「なんですって? 安楽死が、トレンドワード?」
「来年早々、特区構想は実現化します。そうでもしなきゃ、東京オリンピックの財政的な失敗を未だ国も尻拭いできずにいる今、日本は社会保障費で崩壊しかねない。これ以上は消費税も上げられないですし、だからといって法人税を上げる気は、与党には毛頭ないですからね。国民皆保険制度撤廃では選挙に勝てない。だから、あ・ん・ら・く・し。これが社会保障費削減の本丸になったんですよ」
安楽死という漢字3文字が、真子の脳裏に迫ってくる気がした。しかし、国が意図しているのは、社会保障費の削減とは。このなんともいえない蟠(わだかま)りも、明日になれば忘れてしまうのだろうか。言葉の出ない真子の気持ちを察してか、高城はこう続けた。
「澤井先生だってわかるでしょう。何かか国策になるときは、いつだって国民の幸福のためじゃない、金の問題ですよ。だけど、それと死にかけの老人、いや失礼、不治の病に苦しむ人たちの望みが一致するというのなら、それも悪い話ではないと僕は思いますがね。今すぐ苦しみから逃れたい。死にたいと本気で望む人がいるのなら……そうか、そうだ。澤井先生、ほんとに本気で死にたいですか? 安楽死したいですか?」
高城の声が、急に溌剌(はつらつ)としはじめた。
「えっ? ええ、もちろんよ。早く死にたい、自分が自分でいられるうちに。それと、痛いのも嫌。痛くなく死にたいのよ」
「ふうん、わかりました。それならウチの誌面で面白いことができるかもしれません。ねえ澤井先生、<安楽死特区>に入りませんか。手続きはウチでなんとか手を回します。元祖おひとりさま女流作家の澤井真子が、認知症で安楽死希望。うん、いける。これは新しいですよ。国にとっても悪くないテーマだ。これ以上認知症の人が増えると、これまた日本は破綻の一途ですからね。どうしようかな、まずは厚労省に電話して……」
話の展開の速さに真子はついていけなくなる。あんらくし、とっく。
「ごめんなさい。ちょっと話が見えないわ。私、混乱してきたわ」
「いえね、シンプルな話です。澤井先生がご自身の認知症の進行が恐ろしく、安楽死したいのなら、今度できる<安楽死特区>の住人として入ってもらって、その体験談を、ウチの雑誌に連載をお願いしたいと言っているだけです。先生の死にたいという希望を叶えましょう、という話です。そうなったら、NHKと組んでドキュメンタリー撮影もありだよなあ。NHKスペシャルでがつんとやればベストセラー確実ですよ。あとは国がテレビ撮影を許可するかどうかだな」
NHKスペシャル。あれはいつだったろう、令和になってからだったろうか。
難病に苦しむ日本人女性がわざわざスイスに行って安楽死をするという放送をしたことがあったはずだ。神経難病で寝たきりになったその50代の女性も、たしかおひとりさまであった。点滴で毒薬を彼女の腕に入れる前、安楽死を手助けするスイスの女性医師は、カメラの前でこう呟いていた。――日本に安楽死法があれば、彼女はもっと生きられたのに、と。そして彼女はその医師に毒を静脈に入れられて数分で、眠るように静かに逝った。思えば、真子が安楽死への憧れを密かに抱きはじめたのは、あの番組を見たことがきっかけではなかったか。
テレビカメラの前で美しく眠るように逝った彼女の顔が、自分の顔に置き換わる。あ・り・が・と・う、と大切な人に言いながら人生を終わらせる。なんと理想的な死だろうか。
・
こうして真子は、まだどの作家もやっていない。”新たなテーマ”を見つけた。高城との電話を切った美和は、真子を横目で見るとこう言った。
「真子先生。意外です。そんなに死ぬときに痛いのが、嫌ですか? それは、先生が無くした息子さんをさんざん延命治療で苦しめたから? 息子さんの苦しみを見て、自分はあんな死に方はごめんだ、ずっとそう思って生きてきたんでしょう?」
「なんで、すって?」
どっと汗が噴き出た。誰にも話していないことだ。絶対に。話したことは忘れても、話してはならないことは、覚えている。
「何を言っているの? 美和ちゃん?」
「嫌だ、先生が以前、話してくれたじゃないですか。もしかして、それも忘れちゃったとか?」
とたんに真子は病気が一気に進んだように感じられた。