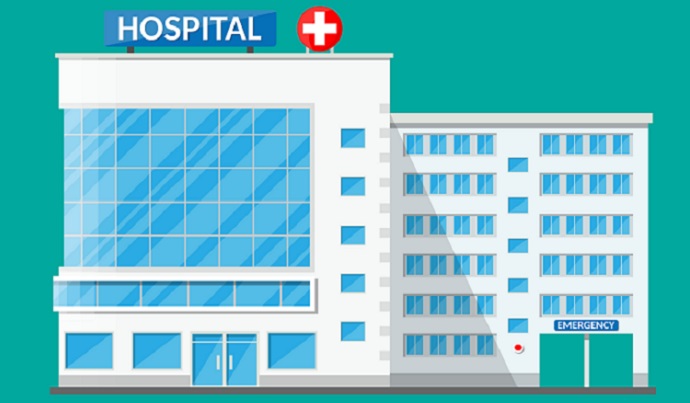
死ぬ瞬間
ウィキペディア(Wikipedia) より
『死ぬ瞬間』(On Death and Dying)は医師のエリザベス・キューブラー=ロスの著書。1969年に発表され大きな話題となった。日本では川口正吉の訳で読売新聞社より1971年に刊行された。
【死の受容のプロセス】
キューブラー=ロスは200人の死にゆく患者との対話の中で以下の5つの死の受容のプロセスがあることを発見した。ただし、すべての患者が同様の経過をたどるわけではないとしている。
・否認・隔離
自分が死ぬということは嘘ではないのかと疑う段階である。
・怒り
なぜ自分が死ななければならないのかという怒りを周囲に向ける段階である。
・取引
なんとか死なずにすむように取引をしようと試みる段階である。何かにすがろうという心理状態である。
・抑うつ
なにもできなくなる段階である。
・受容
最終的に自分が死に行くことを受け入れる段階である。
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
『人は、人を浴びて人になる―心の病にかかった精神科医の人生をつないでくれた12の出会い』
夏苅郁子/著 ライフサイエンス出版 2017年発行
「医師」として生きると決めた時 より
「ホスピス」を知っていますか。
末期のがんなどの病気のために余命が迫った人の痛みをコントロールしたり、精神的な支えを行う医療施設のことである。
私は医師になってしばらくして、日本で2番目にホスピスを開いた精神科医の柏木哲夫先生(現・ホスピス財団理事長)の病棟回診を、3年間見学させていたたいた。私と柏木先生とは出身大学も違い、面識も何もなかった。そんな私が、柏木先生の回診をなぜ3年間も見学できたのか? きっかけは、私が出した1通の手紙だった。
その前に当時のことを少し振り返ってみたい。
私が研修医だった頃、キュブラー・ロスというアメリカの精神科の女性医師が書いた『死ぬ瞬間――死にゆく人々との対話』(読売新聞社)という本が世界的なベストセラーになった。1970年代、終末期にあるがん患者へのインタビューをベースに、キュブラー・ロスががん患者の心理分析を記した本である。
当時の日本では、進行がんの場合は本人には病名を言わないのが暗黙の了解だった。そうした状況下でのこの本の出現に、日本中が驚いた。
・
死にゆく患者さんと接するとはどういうことなのか、それは大変なことだったにもかかわらず私は何の動機付けもなく、言われるままに第15病棟へ毎日通った。
今考えればとても不遜なことであり、当時のホスピスの患者さん達には本当に申し訳なかったと思っている。「お役に立とう」とも考えず、何の心構えもない私は、当然ながら患者さんにどう話かけてよいか全く分からなかった。
研究目的に私を派遣した教授は、数ヵ月たってもレポート1つ論文1つ書かない私に腹を立て「何をやっているんだ!」と怒り出した。
入院している方々は、全員が余命数ヵ月の方だった。私よりはるかに年上で、骨と皮だけのような身体を横たえ、鋭い目線で私を見返してくる。
・
3年間通ったホスピス、そこに本当に死が身近にある場所だった。柏木先生や介護スタッフの方と一緒に、何人もの方をお見送りした。このホスピスはキリスト教の精神に基づいて建てられたものなので、病棟内には「祈りの部屋」があった。そこに入り、祈っているのは、患者さんや家族よりもスタッフの方が多かった。
その人の人生の最期の時間をより良いものにしたいと、医師も看護師もワーカーさんも懸命だった。懸命なだけに、葛藤や苦しみも多いことが伝わってきた。
ある患者さんの今後の治療についてスタッフ内で意見が合わず、担当医師が泣いている姿も見た。そのたびに、カンファレンス(会議)が開かれ、それぞれが自分の心と向き合い納得するまで話し合っていく。
「人が人を支えるということ」……それはとても重く苦しいのだということ、それでも人は続けていく強さがあり、そうした人を支えるのもまた人であることをホスピスから教わった。死はすべてを失ってしまうけれど、大きな別なものをもたらしてくれるのだと思った。死にたいする私の考え方は、大きく変わった。
死が見えてきたことで、生きていることの意味、生きていけないことの意味も少し分かってきた。私は、精神科医としてのこれからの自分を考えた。
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
どうでもいい、じじぃの日記。
私は大人の発達障害だ。これまでほとんど人と交わりがなく生きてきた。
今まで生きてきて、何か人の役に立ったことはあったのだろうか。
後は死が待っているだけだ。
しかし、「ホスピス」とは関係ないけど、「ブラックホール」って不思議だなあ。