月の起源
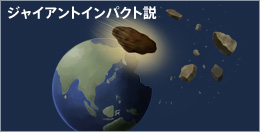
月をめぐる謎
See the moon 2007 三菱電機サイエンスサイト DSPACE
●4つの起源説
双子説の場合、地球と組成が似るはずですが、実際には月には鉄や揮発性元素に乏しいです。 捕獲説の場合、巨大な天体を減速させるほどのブレーキをかけることは難しく、ブレーキがかかったとしても、うまいタイミングでブレーキペダルを放さないと、今度は地球に衝突してしまいます。 分裂説の場合、一部が引きちぎれるほど高速回転することは力学的に見て無理があります。 分裂説・捕獲説・双子説とも、月の誕生を矛盾なく立証することが出来ず、そこで登場したのがジャイアント・インパクト説です。 現在一番有力なのはジャイアント・インパクト説ですが、結論はまだでていません。
https://www.mitsubishielectric.co.jp/dspace/moon/mystery/6_b.html
世界はなぜ月をめざすのか
【目次】
はじめに
序章 月探査のブーム、ふたたび到来!
第1章 人類の次のフロンティアは月である
第2章 今夜の月が違って見えるはなし
第3章 月がわかる「8つの地形」を見にいこう
第4章 これだけは知っておきたい「月科学の基礎知識」
第5章 「かぐや」があげた画期的な成果
第6章 月の「資源」をどう利用するか
第7章 「月以前」「月以後」のフロンティア
第8章 今後の月科学の大発見を予想する
第9章 宇宙開発における日本の役割とは
終章 月と地球と人類の未来
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
『世界はなぜ月をめざすのか』
佐伯和人/著 ブルーバックス 2014年発行
アメリカのアポロ計画が終了してから40年余――その間、人類は月に行っていません。
人々のあいだにはいつしか「いまさら月になど行く必要はない」という認識さえ広まってきています。
しかし、それは月での優位を独占しようとするアメリカの広報戦略にはまっているにすぎません。
じつは世界ではいま、アメリカ、中国、ロシアなどを中心に、月の探査・開発をめぐって激しい競争が水面下で始まっています。30~40年後には、月面基地が完成するともみられているのです。
第4章 これだけは知っておきたい「月科学の基礎知識」 より
そもそも月はどのように生まれたのか
今度は、月がどのようにして生まれたのかを見てみましょう。
月の起源には、おもに4つのモデルがあります。「兄弟説」「親子説」「他人説」「ジャイアント・インパクト(巨大衝突)」です。
「兄弟説」とは、月と地球は太陽系の塵が集まって同時にできた、とする考え方で、地球と月の原材料が似ていることをうまく説明します。原材料の1つである酸素には、重さが微妙に異なる3種類の酸素原子16O、17O、18Oがあります。重さが異なる酸素原子は酸素原子の同位体と呼ばれ、太陽のような恒星の中の核融合反応でつくられます。
宇宙誕生以来、恒星は誕生と爆発をくりかえしていて、私たちの太陽系は、数百もの恒星の残骸の集まりではないかと考えられています。そのため太陽系初期には、3種類の酸素原子同位体の割合が場所によってさまざまに異なっています。したがって、ある天体が太陽系初期にどこでできたかによって、3種類の酸素原子同位体の量の比率が異なります。たとえば、地球の岩石と、火星の岩石と、小惑星帯から飛んで来た隕石の岩石は、比率の違いで見分けることが可能です。この酸素原子同位体の比率が、月と地球はきわめて似ているのです。この類推は「兄弟説」ならばうまく説明できます。
しかし、月・地球系のもつ大きな角運動量(すなわち、月が地球のまわりを勢いよく回っていること)が説明できないという問題があります。また、月の核の体積割合が地球よりもはるかに小さいことの説明が難しいという問題があります。
「親子説」は、地球の高速自転によって月が地球から飛び出したとする説です。この考え方は、月全体の化学組成の推定値が地球のマントル組成に似ていることをうまく説明できます。酸素原子同位体比の類似も、もちろん説明できます。しかし、そもそも月が飛び出すほどの高速自転がありえるのかという問題や、かつて高速回転していた形跡が現在の月と地球の運動に残っていないところに疑問が残ります。
「他人説」は、別のところで形成された月が、宇宙をさまよっているうちに地球の引力に捕まったとする説ですが、そもそも実現が難しいのではないかと考えられています。さまよう月を引き留めるほどの強い引力があると、そのうち月は地球に落下してしまいます。ですから、何か特別なトリックを使わなければなりません。たとえば、地球形成初期には地球の大気が月の軌道にまで達していて、月の運動にブレーキをかける効果を発揮し、月が地球の重力にとらえられた頃に、なぜかうまい具合に大気が減ってブレーキがなくなり、それ以上は月は落ちてこなかった、などといった仮定です。不可能というわけではなさそうですが、いろいろなことをうまくタイミングで起こす必要があり、実際にはかなり難しそうなのです。
現在もっとも多くの研究者に信じられている説が「ジャイアント・インパクト説」です。これは、地球形成初期に火星サイズの天体が原始地球に衝突し、宇宙にまき散らされた破片が再集積して月ができたとする説です。ジャイアント・インパクト説であれば、衝突による加熱で月の材料物質を高温にして溶かしてしまえるので、月が地球に比べて水やナトリウムなどの蒸発しやすい成分がほとんど失われていることが説明できます。また、マグマオーシャン仮説の弱点も補えます。月地殻形成モデルの代表的存在であるマグマオーシャン仮説には、深さ数百キロメートルものマグマの海をつくるほどの熱を生み出すには、月のもっている放射性物質は少なすぎるのではないか、という疑問がありました。ところがジャイアントインパクトがあれば、衝突によって発生する熱でマグマの海を簡単につくりだすことができます。
現在、ジャイアントインパクト説はもっとも多くの研究者の支持を集めています。しかし、天体衝突のコンピューターシミュレーションによると、最終的に月となる破片は、もっぱら衝突物である地球外天体の構成物になるのだそうです。そうであれば、地球のマントルと月の組成が似ていることや、月や地球の酸素原子同位体比が似ていることは説明できず、ただの偶然ということになってしまいます。衝突直後に、月と地球の物質を均質化する何らかの現象が起きたのかもしれませんし、そもそもシミュレーションそのものに問題があるのかもしれません。ジャイアントインパクト説にも、まだよくわかっていないことがあるのです。