What is Generation Z?
Z世代
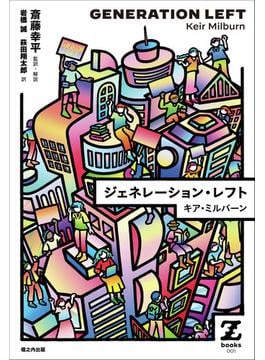
【斎藤幸平】なぜ今、Z世代は「左傾化」しているのか
たとえばアメリカでは、18~29歳のうち51%が社会主義に肯定的という調査もあり、その比率は資本主義(45%)を上回っている。
イギリスの政治理論家、キア・ミルバーン氏が同名の著書で取り上げた言葉で、Z世代(1990年代後半生まれ~)を中心に、左派的な政党・政治家への支持が広がっている現象を指す。
https://newspicks.com/news/6275137/body/
ちくま新書 SDGsがひらくビジネス新時代
竹下隆一郎(著)
SDGsの時代を迎えて、企業も消費者も大きく変わろうとしている。ビジネスの世界は一体どこへ向かっているのか? 複眼的な視点で最新動向をビビッドに描く!
序章 SNS社会が、SDGsの「きれいごと」を広めた
第1章 SDGs時代の「市民」たち
第2章 優等生化する企業
第3章 「正しさ」を求める消費者たち
第4章 衝突するアイデンティティ経済
第5章 職場が「安全地帯」になる日
最終章 SDGsが「腹落ち」するまでに
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
第3章 「正しさ」を求める消費者たち より
ここまでの議論を少し整理しておきたい。第1章では、企業社会に変化を促すSDGs市民たちの動きを見てきた。そうした市民と向き合い、企業が優等生化している姿を第2章で分析した。「市民」と「企業」に続いて、第3章では、新しいタイプの「消費者」について検討していく。彼女たちや彼らもまた、現代ビジネスを変えていく重要なプレーヤーである。
またたく間に形成される「私たち」
ツイッターで欠かせない機能の1つとして「ハッシュタグ」が挙げられる。自分が投稿するツイートに「#」をつけ、それに続けて関心のあるキーワードを入れることで、同じような問題関心を持つ人とつながることができる。「冷凍餃子は手抜きなのか」論争のときは、「#冷凍餃子」や「#手抜き」というハッシュタグが生まれた。その言葉で検索をすれば、多くの人の意見を誰でも読むことができた。
本書では「アイデンティティ」という言葉を、自分の中の「本当の自分」を探しあて、同じような価値観を持った集団を見つけ、社会からの承認を求める際の「尊厳の土台」という意味で使っている。所属集団を見つけるのにハッシュタグはうってつけだ。餃子をテーマに、「ハッシュタグ」という大それたものを議論するのは少々気が引けるが、今まで冷凍食品を使うことで感じていた心の葛藤が、自立した個人としてのアイデンティティに関わる問題だ。冷凍餃子は、現代社会においては大ごとなのだ。
アメリカ在住の文筆家の佐久間裕美子は『We(ウィ)の市民革命』(朝日出版社)で、Z世代などの消費者たちが企業に対し抗議の声を上げる様子を鮮やかな描き出している。彼女や彼らは、銃規制を求めたり、環境問題の改善を促したりすることを重視している。「アメリカでは『私たち』のムーブメントが起きている」ということを同書は活写している。
佐久間氏のこの本でも紹介されているが、総合コンサルティング会社のアクセンチュアは、新しい消費者が「ミー(私)」から「ウィ(私たち)」へと変化している報告書を出した。アクセンチュアによって、世界35ヵ国2万9500人の消費者を対象に2018年に行われた調査では、6割の消費者がプラスチックの削減や、公平で透明性のある雇用環境の確保を企業に求めていることが分かった。これまで消費者は「ミー(私)が欲しいものをくれ」と企業に要求してきたのを対して、現在は「私たち(ウィー)の価値観に沿った理念をサポートしてくれる」ことをビジネスに求めているのだという。
「私」から「私たち」へという価値観の変化は、孤独だと思っていた「私」がツイッターのハッシュタグによって、同じような「私」とつながることができ、瞬時に「私たち」を形成できるというSNS上の現象とも適合的だ。SNSがそうした傾向を加速させているのは間違いない。インターネットは「私」という個人のメディアとして語られがちだが、「私たち」というアイデンティティを形成するメディアだったのだ。ここで注意が必要なのは、さまざまな「私たち」がこうして形成されたとき、異なる価値観を持つ「私たち」同士が衝突する可能性もあるということだ。こうした負の側面は、第4章で詳しく見ていきたい。
Z世代と「SDGs消費者」
さて、本章も終盤になってきたが、「モノ言う消費者」のことを考えるうえで外せないキーワードがある。Z世代だ。1990年代中盤以降に生まれた、2021年現在で10~20代の若者(グレタ・トゥーンベリさんは2003年生まれのZ世代)を指す。この世代は社会課題の解決に積極的だと言われ、労働組合の中央組織である連合の調査によると、10代の7割が社会運動に「参加したい」と答えている。
私自身は、世代ごとに特徴をラベリングするのはあまり好きではないものの、世界的にこの世代は、気候危機やジェンダー平等などの問題に敏感だとされている。はたして、これまでの世代と比べてZ世代は特別なのか。
もちろん、Z世代ならではの「特徴」はさまざまあるが、本当に「特殊な世代」なのかは、ハッキリとは分からないというのが私の答えだ。ベトナム反戦運動や1968年5月のパリで始まった若者たちの社会運動(5月革命)を持ち出すまでもなく、いつの時代も若者は世界の理不尽さに敏感で、よりよい社会を作ろうとしてきた。とはいえ、2021年を生きる若者だからこその特性は確実にある。異常気象が毎年のように起こり、地球温暖化に関する科学的な論争もある程度の決着がつき、「温暖化はうそだ」という言説も随分と減ってきた。県境問題の解決も促すSDGsの目標達成年が2030年というのも大きい。多くの10~20代の若者にとって、10年後は、自分たちが、社会に出て中心的な存在となる時期である。その後の2040年も2050年も、シニア世代と比べたら「現実感」がある。
環境問題だけではない。SDGsでは目標5に挙げれれている「ジェンダー平等」に関して、日本の遅れは特に目立つ。
・
こうした環境問題やジェンダー平等への意識の高まりに加えて、従来の若者との違いを挙げるとすると、本章で見てきたような「SDGs消費者」が多いということだ。
SDGs消費者は、ただ買うだけでなく、「声を上げる消費者」だということを、本章では見てきた。たとえば、環境に配慮した商品を買ったあとに、なぜそれを自分が買おうと思ったのかをツイッターで投稿する人がこれからは増えていくだろう。
Z世代たちは今後、SNSなどを通じて単につながるだけでなく、自らの「個人的なこと」と、他人や他の世代の「個人的なこと」とは違うということに否応なく気付いていくだろう。あるいは、自分と似ているような誰かであっても、実は「個人的なこと」をめぐってズレがあることを発見するだろう。
それによって時には、自分の「個人的なこと」が修正を迫られることがある。他者と対話を重ねながら築いていくのが、私たちのアイデンティティだ。
だが、これまでは良い事例ばかりを見てきた。企業と消費者が互いに影響を及ぼし合って、アイデンティティを強化することは、場合によっては、「私たち」同士のシビアな衝突を生む。企業と消費者がアイデンティティによって強固に結ばれた現代、そこから排除される人たちとの衝突。アイデンティティに傾いたビジネスがもたらす負の側面。これらのことを次の第4章で見ていきたい。