Every Year of Indian Colonialism 動画 YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=yD0dt_f8DIc
British India
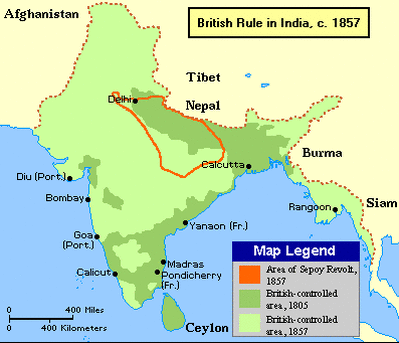
『インドの歴史 (ケンブリッジ版世界各国史)』 バーバラ・D. メトカーフ、トーマス・R. メトカーフ/著、河野肇/訳 創土社 2006年発行
大反乱前後――1848-85年 より
1857年から58年に北インド一帯で起きたイギリス支配に対する大反乱は、インド近代への分岐点だった――と、これまで私たちは教えられてきた。その混沌として破壊的な大反乱は、植民地支配者たちには「暴動」と見なされ、ナショナリストたちにはインドの「最初の独立戦争」と解釈された。しかし、それから長い年月を経た今日では、この大反乱を単独の出来事としてではなく、長期間にわたる重要な変化の中で起きた出来事として見ることができる。また、そのような見方をすれば、インド国内における出来事や特定の人々ばかりではなく、近代の世界情勢の変化との関連でインド史を理解することができる。近代は決してヨーロッパに「たまたま生まれ」たわけではなく、また、その後でインドに移植されたものでもない。世界史の変化の多くは、国どうしの関係の中から生まれたのである。
近代の技術的な革新、なかでも運河、鉄道、電信の利用は、インドでもヨーロッパより数年遅れて始まった。また、近代の政治的革新、なかでも統治権の確立、国民の調査と掌握、教養ある市民層の育成を目的とする制度づくりは、大まかに言えば、インドとヨーロッパの数ヵ国でほぼ同じ時期に実施された。事実、イギリスの近代的習慣や制度のいくつかは、インドの事例に促され、あるいはインドの事例をそのまま移入したものだった。公営の公園墓地は、すでに見たようにインドで始まり、イギリスがその例にならったものである。また、イギリス文学を教育科目にすることも、国による各種の科学研究や国土調査の施設設立も、まずインドで行われた。しかも、イギリスが近代国家の本質的な特徴の1つである政教分離に踏み切ったことも、植民地の統治と決して無関係ではなかった。インドでもイギリスでも、政府による政教分離方針の決定と同時に、かつて例を見ないほど大衆化した新しい宗教団体が誕生した。また、選挙制度が拡充されるにしたがって、公の場における宗教の扱いが問題化した。特に両国の経済は密接な関係を保ち、その度合いが時代とともに強まった。
たとえインドの近代化が1848年から始まったとしても、当時のインドとヨーロッパとの間には重要な相違点があった。
・
今日のたいていの歴史家は、インドの近代性はイギリスの厳格な植民地政策によって決定的に、あるいは歪められて、形成されたと考えている。英領インド時代には、インドの国家的統一・安定、体系的な法制度、英語教育、公共事業、一連の社会改革はすべて「イギリス支配の恵み」と安易に解釈された。しかし、そうではなかった。当時すでにヨーロッパの近代性を批判していた知識人――特にインドとイギリスの知識人――は、インドのそのような改革が植民地政策による人種差別、軍国主義、経済的搾取などの欠陥をともなっていることを指摘していた。とりわけ「イギリス支配の恵み」に暗い影を投げたのは、イギリス人がインド人の自立能力と自立への願望を軽視し、イギリスが「永遠に偉大であるという幻想」を抱いたことだった。確かに、1830年代、40年代のイギリスの統治理念は、基本的には、世界の人類の幸福と進歩への希望というヨーロッパ啓蒙運動の精神に基づいていた。しかし、その時代でさえ、福音主義的で功利的な改革の中に専制的な性格がはっきりと見られた。そして、インド統治は1870年代までには全般的に様変わりし、なかでもイギリス人官僚のきわめて権威主義的な態度が目立つようになった。彼らのほとんど全員が、イギリス人とインド人とは本質的に異なる人種であり、「優越した人種」であるイギリス人がインド人を永久に支配するのは当然と確信していた。